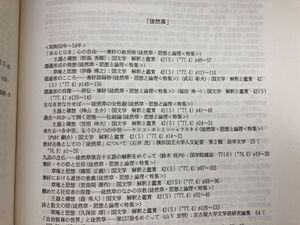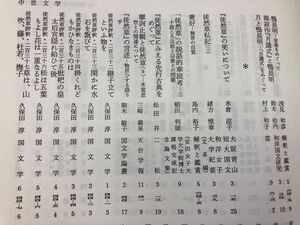続・ネットが無かった30年前の学生はどうやって勉強してたのか、という想い出がたり 情報環境編
前半はこちら;
https://egamiday.sakura.ne.jp/egamiday3plus/20240820/318/
その続きのよもやま話です。
●ワープロをくくって運ぶ
当時は、学生の身分でもがんばってバイト代を貯めればワープロを買えたくらいだったので、自分もがんばって買いました。ワープロ専用機というやつですね、でっかくて重くて画面が小さくて、データはフロッピーディスクに保存する、という。
まず、でっかくて重いので、図書館や教室には持ち込めないです、モバイルではない。基本的に、紙でコピーとったりノートに書いて持ち帰ってきたものを、家で入力するためのツールです。前述のように、論文情報を収集して、その書誌データをワープロのデータベース機能の中に入力するんですが、そのリストを、大学へは持ってけないけど図書館やどこかやで参照はしたいから、自宅でリストをインクリボンで紙に印刷して、その紙束をカバンに入れて持ち歩いてました。註釈が永遠に要りそうですが、ワープロ専用機のデータを保存したフロッピーディスクを、大学のパソコンに入れて読めるような互換性はないし、そもそも大学に学部生が自由に使えるパソコン自体がまだ稀少だし、肝心の講義室や図書館では使えないわけなので、データ入力したあとでもメインのメディアはまだ全然紙のままでしたよね。
あと夏休みに1ヶ月くらい帰省するのに、そのでっかくて重いワープロを持って帰りたくて、ロープでくくって肩紐をつけて、18キップで鈍行列車に持ち込んで12時間かけて運ぶ、という苦行もしてました。じゃあなんで宅配にしないのかと言えば、そんなところにお金かけれるなら18キップで帰省しないです。
そのワープロも、でもやっぱり当時はまだ過渡期の終盤くらいの感じで、学部によっては卒論はワープロ禁止、先生によってレポートはワープロ禁止、みたいな話もまだちょいちょい聞いてました。さすがに自分が卒論を出す頃にはあまり聞かなかったかもしれませんし、ていうか、これはなんとなくの印象ですが、文学系の先生たちって文系の他の分野の先生よりもワープロやパソコンを導入するのに抵抗ない、むしろ早いほうだったんじゃないかという気がします。自分の文章を自由に活字化して自由に印刷できる、って文学系には大好物のツールだろうと思うので。
とはいえ、全学生や全先生がワープロを持ってるわけでもないので、授業で配られるレジュメ(先生作のも学生作のも)はまだまだ手書きだし、もっと言うと文学系のレジュメだと本文テキストや参考文献を紙でコピーして該当箇所をハサミと糊で切り貼りして作るので、そこにワープロの文字までわざわざ印字してから切り貼りするのはめんどくさく、結局はだいたいのレジュメが手書きになりますよね。そんなんよう作ってたな、マジでいま便利すぎる。
なお(ワープロ専用機ではない)パソコンのほうについては、小・中でMSXを使った時期があって以降、久しくご無沙汰でしたが、ちょうど1993年くらいに学内にパソコンを置いてある教室ができて、文学部の学生であっても限定的にIDを発行してやる、そこの教室で使わせてやる、週1の情報の授業で使い方を教えてやる、みたいな、いまから考えるとけっこう出し惜しみしてるなという感じの環境があって、そこで、読みづらいちまちました画面とリアル脱出ゲームのようにわかりにくいユーザインタフェースで使える電子メールというのがあって、週1で遠隔の理系の友人とメール送りあいとかしてました。なんかもう思い出すだけで肩が凝るようなパソコン体験で、結果として得られるのは牛の毛ほどのリテラシーですけど。
それから2年後くらい(院生)に、所属研究室のWindows95パソコン(共用)に入ってる一太郎で、修論書きました、その頃になるとフロッピーディスクを持ち歩けるようになるという(注:自宅のワープロとの互換性はもちろんない、あれどうしてたんだろう??)。さらにその2年後くらいに、図書館の閲覧スペースに自由にインターネットが使えるパソコンが数台置かれ、なんか年中コミケやってる(註:好きなことを執筆してパブリッシュできる環境、の意)ようなところなんだな、という認識のもと、あ、たぶん自分はいち早く”あっち側”に行かなければならない、という本能的な直感を得て、その翌年くらいにとっとと就職して得たサラリーでWindows機を購入し、自宅から接続したインターネットでホームページを発信するに至る、というのもこれも完全に別の話ですね。
●歩くKansai Walker・人間食べログ
なんだっけ、そんなふうにパソコンもインターネットもまだまだ夜明け前で、携帯電話も平野ノラと大差ないくらいだったので、大学での勉強だけでなく、日常生活もデジタルとはほど遠い感じだった、という導入です。
そういう感じだから、カバンには常に本が何冊か入ってる、これはいまも入ってますが、新聞・雑誌の類こそ当時は必ず入ってたという感じですね。新聞なんか、当時は貧乏下宿生であっても当たり前のようにお金払って取ってたし、いまスマホ見るような隙間のタイミングで当時見てたのが新聞・雑誌だったなと思うと、まあそりゃ売れなくなりますよね。
空き時間に触れるメディアとして、さほど音楽を聴く習慣のなかった自分でさえも、レンタル屋さんでCD借りてカセットにダビングして流してるということはなぜかやってて、そういう時に行くのがツタヤだったんですけど、そういう習慣もなくなっちゃったしみんなもレンタルビデオは配信で見るようになったから、そりゃツタヤさんも図書館商売に手を出すしかしょうがなくなるよな、という感じです。
あと音楽だけでなく、常に耳寂しい「ながら族」だったので、たしか安い携帯ラジオとイヤホンをカバンに常備してたような気がします。中高からラジオはよく聞いてたし、大学の頃もちょうどαステーションの開局が91年で家では流しっぱなしだったはずなんですけど、これもいつの間にか聞くことがなくなったのとインターネットの登場とに因果関係があるかどうか、ちょっとよくわかりません。
あとはカバンに京都市内の地図を常備してた記憶があります、お寺とかよく行ってたし、それこそよその大学や図書館行くのに必要なので。それとよく使う駅の時刻表とか、市バスの路線地図。
それからアドレス帳の類も必ず入ってる、これが無いと友人と連絡取れないからですけど、でもその番号も自宅/下宿の電話番号だし、当時はまだ留守番電話機能がある友人とない友人といたりしたから、連絡が取れたり取れなかったりするし、大学で会った時に「何曜日の何時ころ家に居る?」って確認したり、親しい友人なら取ってる講義やバイトやサークルの曜日時間は覚えてて、居そうな時間に電話するとかですよね。
そんなんだから、どこかへ行く待ち合わせにしても、数日前に会った時に予定をしめしあわせておく、もし待ち時間にあらわれなかったらこうする、何分までは待つとか、先に行くとかまで決めておく。事前に決めずに人に会おうとしたら、とりあえず下宿に行ってみて、居たら会えるし居なかったら会えない、まあそんなもんですよね。
どこかへ行くっていうのも、どこに何があって、何駅から何バスで、何時から何時までやってていくらかかる、みたいなことは全部事前に本や雑誌(ガイドブックやぴあやなんとかウォーカー的なの)で調べておかないといけないか、公衆電話から電話番号案内で番号聞いて、電話かけてそれを聞く、とかいう感じだったと思うんですけど、そういう時、コミュニティというか連れ立ってるグループの中にひとりかふたり、そういう情報にやたら詳しい人とかがいるわけですよね。どこそこでどういうことができて、どういうイベントがあって、どうやって行ったらいい、みたいな人がいると、人気出るというか頼られますよね、歩くKansai Walkerやあって、いやウォーカー言うてるやん、的な。
あるいは人間食べログみたいな人もいて、サークル終わりや勉強会終わりにどっか行こうってなると、近所の喫茶店・定食屋・居酒屋について、あそこは何時からあいてる、何曜日定休、この時間なら空いてて、何人用の席があるから、いまいる人数が入れるはず、って言いながら、カバンから手帳取り出して公衆電話から店に電話して、あ、じゃあ10分後くらいに行きます、っていう。
スマホが無い分、そういうことができる人とできない人では行動の仕方がちがったんだろうなと思います。
情報収集する方はもちろんですが、発信する方はもっとそのできるできないの差はえげつなかったかもしれません。
とはいえ、当時学生が何かを発信するというと、サークルや勉強会の広報や情報発信くらいでしょうか。もちろんネットもSNSも無いから、基本はビラを大量に印刷して、大学内の壁という壁に貼りまくり、教室という教室の机に置きまくる。壁、っていうか掲示板があるにはあるはずなんだけど足りるわけがないから壁に貼るんですけど、その壁にも他のサークルがすでに貼ってあるのを、その上に重ねて貼る、そうすると後日通りかかるとよそのサークルがその上に貼ってあるから、またその上に貼る。そういうのを、今度は清掃員の人が大量にはがして捨てていくので、空いたところにまた貼っていく。それの延々繰り返し、SDGsも何もあったもんじゃないですけど。
あとは自主シンポや演劇の類はだいたい立て看で広報されてましたし、生協書籍部とか近所の定食屋・喫茶店にビラを貼ってもらったり置いてもらったり、食堂に三角柱(厚紙を4つ折りにして三角柱をつくって、側面におしらせを書く)を置かせてもらったり、とにかくネット以外のありとあらゆるアナログメディアを駆使してという感じですが、検索してヒットするというわけではないので、伝えたい相手がふだん見る場所通る場所はどこだろうというのを探しては、そこに情報を投げて行く、という感じです、そういう意味での発信リテラシーは当時も必要だったんだなと思います。
あと、校舎内にフリーの黒板があって、いろんなサークルや勉強会が、次の例会は何月何日何時からどこどこ教室です、みたいのを自由に書きこんで、通りがかりにそれを見て確認するし、なんなら、へー、そんな勉強会あるんだ、催しあるんだ、って興味持って顔を出しに行く、みたいなこともよくありました。
そういうところに、いまでは考えられないですけど、代表者や世話人の自宅の電話番号とか書いてあるんですよね、でも別にそんなのふつーだったと思います。壁に貼ってあるビラにしたって、連絡先たる一学生の下宿の電話番号(注:たぶん自宅生はさすがに忌避してたと思われる)が書いてあって、なんなら勧誘目的のビラだと、ビラの下の端っこに細かく縦に切れ込みを入れて、切れ端のひとつひとつに名前と電話番号が書いてあって、要は興味ある人はそれちぎって持って帰れるというやつですね。そんなのは学内の至る所に貼ってあり、バイトのお知らせとかもそういう感じで貼ってあって、あたしがお世話になった編集プロダクションのバイトもそうやって見つけました。いまだとQRコードとかになるんでしょうね。
●結論:インターネット万歳!
総じて、情報を探す/入手するのが、困難だったり時間かかったり不安定だったり、あるいは接する情報が限定されてたり。とは言え、こういう話になると、現代と違ってネット情報が氾濫しておらずフェイクもなく厳選されていたのでは、ということになりがちかもしれませんが、厳選されているということとそれが正しいかどうかというのは別の問題であって、接する情報が限定されていると正しいかどうかの検証すらできないので、そりゃまあ、入手できるなら多くて多様であるにこしたことはないです。
ただ違いがあったとするなら、なんとなくですけど、当時は、情報がまちがってたら、まちがってたね、で終わってた気がします。わからなかったら、わからなかったね、連絡取れなかったら、取れなかったね、会えなかったら、会えなかったね、で。もちろんそれは日常生活や学生の勉強レベルの話ですけど。卒論や修論くらいだと、どこそこのあの本やあの資料は確認できてない、ってなった時に、あの本は手に入りにくいからね、あの資料持ってるあそこは閲覧厳しいからね、という時代から、デジタルアーカイブでもNDLデジタルコレクションでも見れるのになんで確認してないんだ、っていう時代に、いやもちろん見れるほうが圧倒的にいいんだけど、一方で情報が入手できないことやそれに付随するトラブルに、そこまでシリアスでもカリカリもしてなかったような気はします。それはたぶん、「これで探せたことになるのか」「これで見つからなかったと言えるのか」がわからないというか、わかりようがなかったので、適当にあきらめてたっていうことなのかなと。
家電なんか、だいぶ適当に買ってましたよね、店に行ってそこに置いてあるものをそのまま買って帰ってくるくらいだったのが、いまだと山ほどある機能をネットで見比べて、100円なり1000円なり安いものを必死に探して、ってどうしてもなっちゃう。
探しやすさ、見つかりやすさ、アクセスしやすさはいまのほうがもちろんいいんだけど、反面、見つけられなかったとき、まちがってることに気づけなかったとき、気づけなかった人の責任になる、しかも大量のゴミ情報をふまえたうえで、っていうんだったら、そのあたりの世知辛さはかつては無かったのかもしれない。
参照:「現代人って、諦めるのが難しい。」( https://note.kishidanami.com/n/n97e94cc7ea07 より)
とは言え。
ネットが無かった頃のマシだった点を無理くり探し出したとして、↑たぶんこれだけです。
あとはもう、ね。
いまの、情報が多くて多様で、メディアも複数あって、ツールは探しやすく見つかりやすいほうが、圧倒的に良く、それを知ったからには30年前の状態のほうが良かっただの戻って良いだの、口が裂けても言えないです。
何か調べようというときに、図書館が開くまで待つとか、電話かけて聞くとか、カード目録や国史大辞典を全部見るとか、もう絶対無理です。全部見るとセレンディピティが起きる、っつったって、そんなのは不良がたまに見せる優しさが素敵に見える、程度の与太話に過ぎないわけです。Googleマップ無しでは、海外出張どころか国内旅行すらいまさら無理だと思います、太川陽介じゃないんだから。
カバンに入れる本だって、学生の頃はお金がないから文庫になるのを待ってたものを、いまではスマホのKindleで読めるようになるまで待ってます、文字サイズ大きくしないと、老眼がきついので。そういえばあのころ、年かさの先輩のアドバイスに「研究を仕事にするつもりなら、論文のコピーはB4に拡大しておいたほうがいい、高齢になって読むのがつらくなるから」というのがありましたが、まさかその数年後にはPDFで自由に拡大して読めるようになるとは思いませんよね。
というわけで、デジタル最高!インターネット万歳!、というお話にとりあえず今日のところはしておきます。